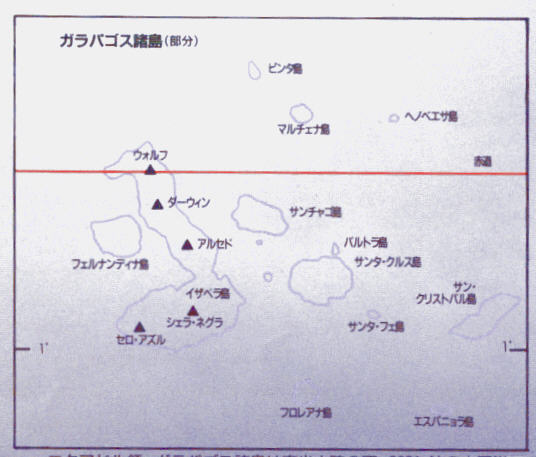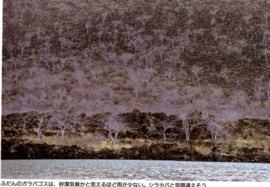|
破壊かそれとも生き物たちへの試練か?
エルニーニョとは、ガラパゴス海域からルー沖にかけて、海面温度が数年に一度、大規模に上昇する現象をいう。スペイン語で「神の子」を意味するこの現象は、地球規模の気候変動を引き起こし、世界中に異常気象を誘発する。一九九七年三月から始まったエルニーニョは二十世紀最大規模といわれる。十一月、その中心地、ガラパゴスを調査するために現地に飛んだ。 「神の子」は確実に野生生物の宝庫を蝕んでいた。
世界の異常気象はガラパゴス海域から始まる! 「エルニーニョ」。この大規模な異常気象が一九九七年三月以降からガラパゴス海域で続いている。エルニーニョは拡大を続け、九七年十一月に入ると、日本の気象庁は今世紀最大のエルニーニョ現象が地球規模で起きていることを公式に発表した。 八二年から八三年に発生したエル・ニーニョもすさまじかった。今世紀最大の規模とされ、「世紀のイベント」とまでいわれた。餌を海に頼っている生物たちが、のきなみ大きな打撃を被った。動物の中には半数以上も死んだり、いまでも棲息数を回復しきれていない種もある。 再び、巨大な規模で発生してしまったエルニーニョ。いったいどれくらいの被害を、ガラパゴスに及ぼすのだろうか? 十年ほど前からぼくは、第二の故郷とも呼べるほど通い詰めているガラパゴス。ふだんでも餌が限られ、ぎりぎりの生き方をしているガラパゴスの動物たちは、どうしているのだろうか。思いたって二週間後には、一路ガラパゴスに向かっていた。 十一月六日、飛行機の窓からいよいよ島影が見え始めていた。 ふだんのガラパゴス(上)と スカレシアの林に進入してきた帰化植物たち(左)とエル 南米大陸の西、九百六十㌔沖の太平洋にガラパゴスはある。エクアドルの首都キトからジェットで約二時間。ガラパゴスの玄関口、バルトラ島に到着。そこから船やトラックを乗り継いで、諸島で二番目に大きなサンタ・クルス島へと向かった。 島の頂上付近は雨雲でおおわれ、かなりの雨が降っているようだった。いつもだと乾季のはずなのだが。
雨をうらやむガラパゴスアシカ 翌朝、島の高山地帯を訪ねた。高山といっても標高八百㍍にみたない地域だが、海岸地帯より十八度も気温が低く、年間の降水量も平均で千四百㍉になる。 ちなみに、サンタ・クルス島北部の海岸地帯での降雨量は年間百㍉ほどしかなく、これはアラビア半島の砂漠と、ほぼ同じような気候だ。 高山地帯では肥沃な土地を利用して牧畜業が営まれているが、例年四月になると、低地から高山地帯へとゾウガメが移動してくる。 これは食料の草を求めての移動だが、高山地帯に住む人の観察によると、今年は山まで上がってくるカメの数が非常に少ないという。雨量が相当多く、ゾウガメは山の中腹でも十分に食料が得られるということのようだ。
悠然と草原を闊歩するゾウガメ 「いつもだと五十頭も現れるんだがな。今年は、十頭ほどの体の大きなオスしか来ていないよ」 と、山頂近くに住む牧場主が話してくれた。 雨がかなり降っている。大陸から移入された牧草が、背丈ほどの高さでびっしり生い茂っていた。いつもなら、山でも枯れ草が目につたものだが、今年は雨で景色が一変している。森に餌が豊富なせいか、フィンチなどの陸鳥たちは繁殖に大忙しだった。 山から降りて、ほかの島々に上陸してみることにした。 サウス・プラザ島はサンタ・クルス島の東にあり、二十分も歩けば一周できてしまう。リクイグアナが棲息していて、ふだんなら乾季に起こる食糧不足で、痩せ衰えている時期である。しかし、エルニーニョですでに雨が降っているらしく、みんな丸々と太っていた。リクイグアナの主食であるウチワサボテンも水分を吸い過ぎ、ついに体をささへきれなくて倒れているウチワサボテンが目についた。 根腐れもおこしている可能性がある。 「もう食いきれねー」 とばかりに、リクイグアナは倒れたサボテンには目もくれず、まったくの満腹状態。 さらに北へ、船で一時間。グンカンドリの繁殖地で有名なノースセイモア島へ。
ウミイグアナの親子 一番に気がついたのは、痩せこけたウミイグアナだ。主食である海藻はどうなってしまったのか。海岸を歩いてみると、好物の緑藻がほとんど消え、食べ慣れない熱帯性の海藻に置き換わってしまっている。飢えに耐えかねた彼らは、陸上の植物を食べていた。肋骨が浮き出て痩せ細ったウミイグアナたち。岩の上にへばりついて、ほとんど動かない。ただ、目だけが時々まばたきするだけ。その周辺で死んだメスのイグアナもたくさん確認できた。 グカンドリの繁殖地も歩いてみた。小枝を集めて作られた、直径八十センチもの巣があちこちに。だが、ヒナが無事に成長している巣は四ヶ所にしかすぎなかった。例年よりかなり少ないようだ。
アオアシカツオドリの親子 こんどは、すぐ近くのモスクエラ島へ移動。島は白砂の丘からできていて、ガラパゴスアシカの繁殖地となっている。三つのハーレムを観察した。赤ちゃんが極端に少ない。過去に何度となく訪れている所だが、様子が変だ。子どもの死体があちこちにある。白骨化してないから、そんなに日がたっていないのだろう。赤ちゃんは多くても三頭ほどで、一頭しか発見できないハーレムもあった。 海に餌を頼っている生き物たちが、飢え始めているのは明らかだった。アシカの状況をもっと見るために、大きなコロニーがあるサン・クリストバル島へ行くことにした。 サンタ・クルス島から船で南東へ約六時間。近くの島には、アホウドリの営巣地で有名なエスパニョラ島もある。 「これからは水中も見てみるぞ」 と、海中の異変を直接この目で確かめようと決めていた。 サン・クリストバル島南端にあるロベリアビーチ。全長三㌔ほどの岩礁と砂浜が続く。やはり、アシカのコロニーが変だ。 赤ちゃんが四十頭ほど、置き去りにされていた。数時間以内に死んだと思われる赤ちゃんが一頭。部分的に白骨化したアシカが六頭。成獣の死体が三頭。ここも飢餓だ。餌となる魚が激減し、アシカたちは餌を求めていつもより遠くへ行っているようだ。親たちの疲労は相当なものだろう。 このまま高水温が続けば、いっそう深刻な事態が起きるにちがいない。さらに雨が追い討ちをかける。赤ちゃんの体を冷やしてエネルギーを奪い、病気の蔓延を助長する。ちなみに、八二年から八三年にかけてのエルニーニョでは、半数以上のアシカが諸島から姿を消した。 翌日、エスパニョラ島プンタスアレスに移動。砂浜には、産まれたばかりの痩せこけたアシカが八頭。 親が付き添っていたのは、二頭だけ。かなり衰弱している。痩せこけた子どもの集団も近くで発見。水際でほとんど動かず寝そべっていた。 突然、枯れたブッシュの中から体長一㍍ほどの巨大なアホウドリが現れた。まだ飛べない子どもだった。もっといるはず、と探し回り、さらに三十分後。もう一羽、子どもを発見。フワフワした羽毛が、可愛い。 なんでも、テレビ番組「セサミストリート」に登場する「ビックバード」のモデルが「この子」らしい。 訪問客に開放されていて、アホウドリを観察できるようになっている場所はわずかだ。この二ヘクタール程の広さの営巣地に、毎年二十から三十つがいが訪れる。ほぼ、つがいの数だけの卵が産み落とされる。卵は三百㌘もあり、かなり大きい。 午前中に親鳥を見つけることはできなかった。漁に出ていたのかもしれない。捨てられた卵三個確認。 日暮れの六時まで、親鳥の到着を待ってみることにした。 四時過ぎ、三羽が戻ってきた。 その三羽はほぼ同時に同じ場所に着陸し、十分ほどたってから、それぞれいつも休憩に使っている場所へ歩いていった。 日暮れまで待ってみたが、結局、この三羽の到着がすべてだった。 最初に見つけた二羽の親鳥は確認できなかった。 育っているヒナは数羽で、捨てられた卵がやけに目についた。 海水温の上昇によって、いつもの魚場で鳥が食べられる魚が極端に減っているらしい。アホウドリの親は、一回に二㌔もの餌を子どもにあたえなくてはならないのに。 フロレアナ島沖チャンピオン島で潜ってみた。島の北側、水深十五㍍から二十㍍海底で、一面に続くサンゴ群落を発見。 だが、ほとんどが死滅していた。ダイビングガイドによると、八二年に発生したエルニーニョの被害だという。 再生しているサンゴもあったが、回復率は十パーセントにも満たないようだ。 生きているサンゴの種類は、ほとんどがガラパゴスシコロサンゴ。さらに、魚の群れが以前よりもずっと少ない。 船をデビルズクラウン岩礁に移動させ、再び潜水を開始。 十五㍍ほどの海底にフジツボの死骸が散乱していた。世界最大級で、十センチ以上もの高さに成長するガラパゴスフジツボだった。 月日がたって黒くなったものから、ごく最近死んだと思われる白いものまで、まるでフジツボの墓場だ。 翌朝、フロレアナ島の北、プンタコーモラント岬に到着。船近くに一羽のペンギン。干潟近くの樹上やハシラサボテンの上では、フィンチが巣作りに忙しく飛びまわっていた。 通常なら、雨がいくらか期待できる十二月後半から三月にだけ、しかも餌が豊富な年のみ繁殖するのだが………。 上陸地点とは反対側の砂浜に降りてみた。 そこには度肝を抜かれるような光景が広がっていた。 何とアオウミガメが砂浜で交尾をしていたのだ。 海面での交尾は何度となく船や岸壁から観察したことがあるが、まさか陸上にまでオスが追ってくるとは。 さらに、アオウミガメが十二頭も上陸していた。日がまだ高いのに、いったいどうしたというのだ? 一般的にウミガメは、メスだけが夜の暗闇にまぎれて上陸し産卵する。海で何が起きているというのだ………。 ふだんよりかなり早いアオウミガメの産卵も確認された。 ウミガメを含めたハ虫類は、温度変化にたいし敏感に反応するという。おそらく、エルニーニョによる海水温の上昇が、アオウミガメのライフサイクルを乱しているのだろう。 船は一路、諸島で一番大きなイザベラ島をめざした。島の西海岸を移動中、船は二本のルアーの付いたつり糸を引きながら走った。 午後四時ころ、ルアーに大きな魚が。シーラである。地元の人たちは驚いていた。シーラは暖かな海の魚で、南米からの冷たい海流に洗われるこの海域では、めったに捕れる魚ではない。 船は夕方、ティグスコーブの入り江に錨を下ろした。ここでは、夜の水中を見てみることにした。夜八時、船から真下の海底水深九㍍へ、一気に潜水。 砂地の海底には、ウニに近い種類のスカシカシパンがいっぱい。海底にたどりついても水が生あたたかい。水温は表層と同じ二十七度。 いつもなら表層は二十三度ほどで、水深一㍍より深くなると五度ぐらい冷たくなる。 「バシ! バシ! ガツン」 突然、何かがぶつかってきた! さらに、 「ガリ! ガリガリ!」 何かがぼくのダイビングスーツを噛んだ。 犯人はアシカだった。一瞬、腰が抜けそうになった。 ここのアシカたちにも、飢えが始まっているのかもしれない。しかし、ホウジロザメのように人間を食べてしまうことはない。アシカが探し回っているのは、大きくても体長三十センチほどの魚だ。五年前にも同じ所で潜ったが、前は大群で現れた魚が、まったく見かけられなかった。出会ったものといえば、アシカにはとても食べられそうにないフグやハリセンボン、アオウミガメ、ハナギンチャク、カスリモミジガイだ。 二日後、船は東へ向かい、サーフビーチが続くサンチャゴ島ジェームス湾に到着した。徒歩十分、北側の岩礁にオットセイのコロニーがあった。 わずか二十頭しか確認できない。赤ん坊は一頭。少なすぎる。 何かがオットセイに起こっている。 前回のエルニーニョで、一時オットセイは三割以下に減少していた。その後、徐々に回復し、現在は元の数まで戻ったというのだが………。 ガラパゴスオットセイはアシカよりもひとまわりほど体が小さい。潜水能力はアシカより劣り、あまり深く潜れないという。そのぶん、餌を採るチャンスも少ないのだろう。こんどの異常気象は、オットセイを再び絶滅の一歩手前に追いつめてしまうかもしれない。 船からサンチャゴ島を見上げると、スコールを呼ぶ真っ黒な雲が山頂からこちらに向かってきた。スコールに打たれる前に、船をさらに東へ移動させる。 島の北東に位置するサリバンベイの溶岩台地に上陸。 約百年前に噴火で出来た真っ黒な玄武岩の台地が噴火口から海まで達している。幅一㌔から数㌔、全長十㌔にも及ぶ壮大な景観。乾燥と赤道の焼け付くような日差しは、生き物の存在を許さない。いつもは岩の上で目玉焼きが出来てしまうほどの環境が激変していた。太陽を遮断する雲がいつもあり、スコールが溶岩台地を冷ましている。この台地でいままで一度も見ることがなかった植物もはじめて目にした。
漁船をつけまわすグンカンドリ 船は南に向かった。出発地であるサンタ・クルス島の山々がしだいに見え始めていた。途中、漁船に出会う。漁船にグンカンドリが群れていた。 漁師がさばく魚のおこぼれをもらおうと集まっているのだ。 「しょうがない奴らだよ。今年はよっぽど餌が取れないんだな」 「いっぱい追いかけてくるよ。こっちも目当ての魚はあまり捕れていないんだけどね」
オスは紅い喉袋 九八年五月、いまだにエルニーニョは世界的規模で続いている。ガラパゴスでの全体的な被害状況はまだわかっていないが、一月あまりのガラパゴス滞在で一番に感じたことは、やはり海に餌を頼るウミイグアナ、アシカ、オットセイ、それに海鳥たちの危機的状況である。長期にわたる異常気象は、海中や海辺で生きている生物たちの体力を確実に消耗させていた。
餌をねだるガラパゴスペリカン これからも続くとみられる雨は、動物たちの弱った体に病気を蔓延させ、大量死をもたらす危険性を秘めているような気がする。八二年から八三年との間に起きた被害をうわまわらなければよいのだが、と祈るばかりである。 帰化植物の勢力拡大も、深刻な問題である。多量の雨は帰化植物たちにとって絶好の繁殖チャンス。大陸から持ち込まれた植物は、すでにガラパゴス全体の植物の三割を占めるまでになった。 猛烈な勢いで島固有の植物群落を襲っているのは、グアバやカスカレーニア、エレファントグラス、ブラックベリーなどだが、こんどのエルニーニョで分布がさらに広がったのは確実だ。 ウミイグアナや海鳥たちにとっては地獄のようなエルニーニョも、植物や昆虫を食べているリクイグアナ、ゾウガメやフィンチなどの陸鳥たちにとっては、またとない機会だ。めったに味あうことができない餌があり余るほどなのだから、まるで天国だ。いまは可能なかぎり繁殖を繰り返し、子孫を増やそうと一生懸命だが、エルニーニョが終わると、ガラパゴスにはふだん以上の乾季が訪れるといわれる。限りある森の餌は、増えた動物たちをとても養えきれるものではないのだ。エルニーニョの後に試練が待ち受けている。 近年、巨大なエルニーニョばかりが起きている。はるか昔からあるエルニーニョとは違ってきている、とみる研究者も多い。人類が引き起こしている「地球の温暖化」が何らかの要因となって、巨大なエルニーニョを発生させているというのだ。 たとえエルニーニョが来なくても、ガラパゴスでは人為的破壊によって絶滅が危惧されている生物がたくさんいる。諸島の大きさひとつとっても、そこでの繊細な生物生態系の維持はたいへんだ。 巨大なエルニーニョや繰り返される人類による破壊が、地球の遺産ガラパゴスを確実に蝕んでいる。

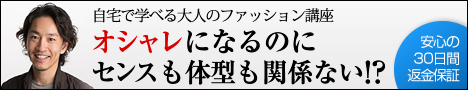
|
|
Copyright (C) by Business Intelligence Network Inc.
|